
妖怪はかつて生物だった?本草綱目がつないだ知と異界の境界線

はじめに:知と想像の交差点にいた妖怪たち
妖怪とは何か。怖い存在か、ユーモラスなキャラクターか、それとも人間の想像力が生んだ自然の解釈装置か。今回は「妖怪×本草綱目」というテーマを通じて、妖怪という存在がかつてどのように「生き物」として理解され、やがて物語や娯楽へと変容していったのかをたどっていく。
1596年:本草綱目、知の金字塔の登場
『本草綱目』は、明代中国の博物学者・李時珍が晩年にまとめた薬物学・博物学の百科事典である。1596年に刊行され、全52巻・1900種類以上の薬物を分類、効能、形態、出典などに基づいて整理している。その中には、「龍の骨(龍骨)」「封(ふう)」「人魚」「火鼠」など、現代では実在が確認されていない存在も含まれている。
これらは当時、民間伝承や古典文献に基づき記録されたものであり、科学的探究と伝承が同居する知識体系の一部として扱われていた。
10〜17世紀:本草綱目、日本へ伝来と受容
『本草綱目』は江戸初期から日本に伝わり、本草学の発展を促した。江戸中期には、日本独自の本草書が次々と生まれる。
とくに重要なのが、1709年の貝原益軒『大和本草』である。これは日本の自然環境や風土に即した薬物学書であり、俗信や民間療法の記述も含まれている。
1712年に成立した『和漢三才図会』(寺島良安)は、105巻にもおよぶ図入り百科事典であり、狒々(ひひ)、魍魎(もうりょう)、川太郎(かわたろう=河童)、人面樹(じんめんじゅ)など、伝承に基づく存在が挿絵とともに解説されている。
18世紀中期:平賀源内と博物学の台頭
平賀源内(1728〜1780)は本草学者、蘭学者、発明家、戯作者として知られ、博物学と伝承の両分野にまたがる活動を行った人物である。
彼は、薬として珍重されていた「龍骨」について、その正体を疑問視し、記録として残している。源内にとって、伝承的存在は、科学と想像の交差点にある文化的事象であった。直近であれば、大河「べらぼう」でも安田顕さんが演じられているのでご存知の方も多いかと思います。ドラマの中でも自身のことを発明家ではなく「”本草学者”の平賀源外と申します」と言ってますね。
18〜19世紀:妖怪の娯楽化とキャラクター化
江戸後期、知の対象としての妖怪は、次第に娯楽や芸術の素材として再解釈されていく。1776年には鳥山石燕の『画図百鬼夜行』が刊行され、多様な妖怪が挿絵と簡潔な説明で紹介された。ここに至り、妖怪は「見えないものの図像化」という文化装置としての役割を果たすようになる。
1800年前後には、読本・草双紙・黄表紙といった庶民文学の中で妖怪は定番の登場人物となり、実在性よりも物語性が重視されるようになった。
19世紀後半〜明治期:近代化と妖怪の周縁化
1868年の明治維新以降、西洋科学が導入され、従来の本草学は次第に衰退する。一方で、妖怪は講談、演劇、後の漫画文化へと受け継がれ、物語世界の住人として定着するようになった。
この時代には、かつて「本草書」に記録された伝承的存在が、完全にフィクションの領域へ移行する傾向が見られる。
おわりに:妖怪とは「知の余白」だったのかもしれない
妖怪は、人間の知識が及ばない自然や社会現象を理解しようとする過程で生まれた存在だった。本草綱目をはじめとする本草書は、そのような存在を「記録」することで、人々が世界をどう見ていたかを今に伝えている。
妖怪は「現実」と「空想」の境界を行き来する知の遺産であり、江戸時代の学問や文化がいかに柔軟だったかを物語っている。かつては生物として認識されたこともある妖怪たちは、今も私たちの想像力の中に生き続けている。
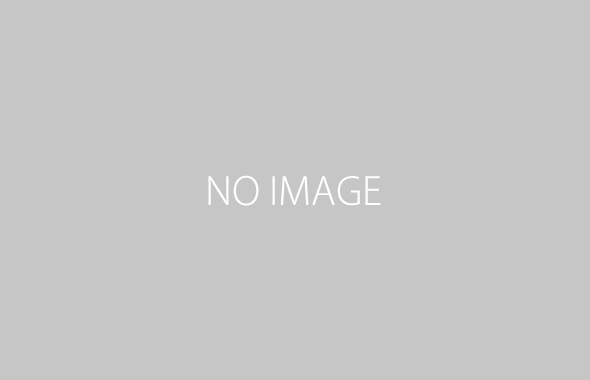

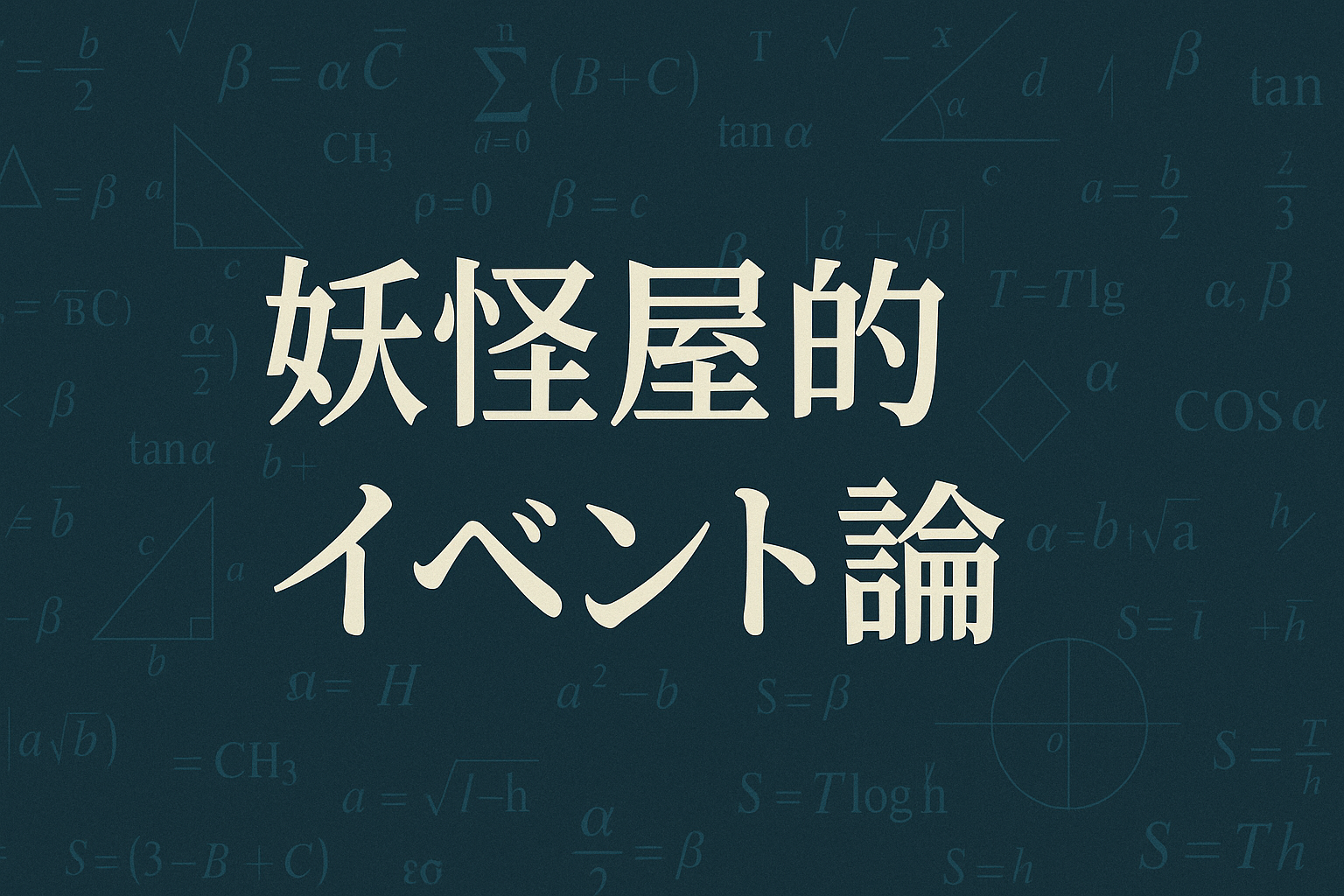
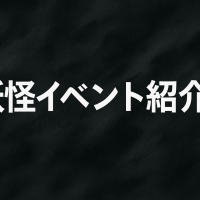

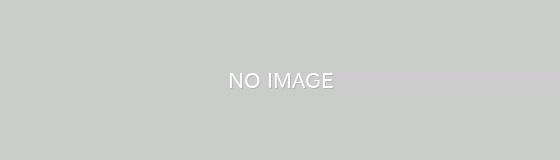


この記事へのコメントはありません。