
イベントの光と影
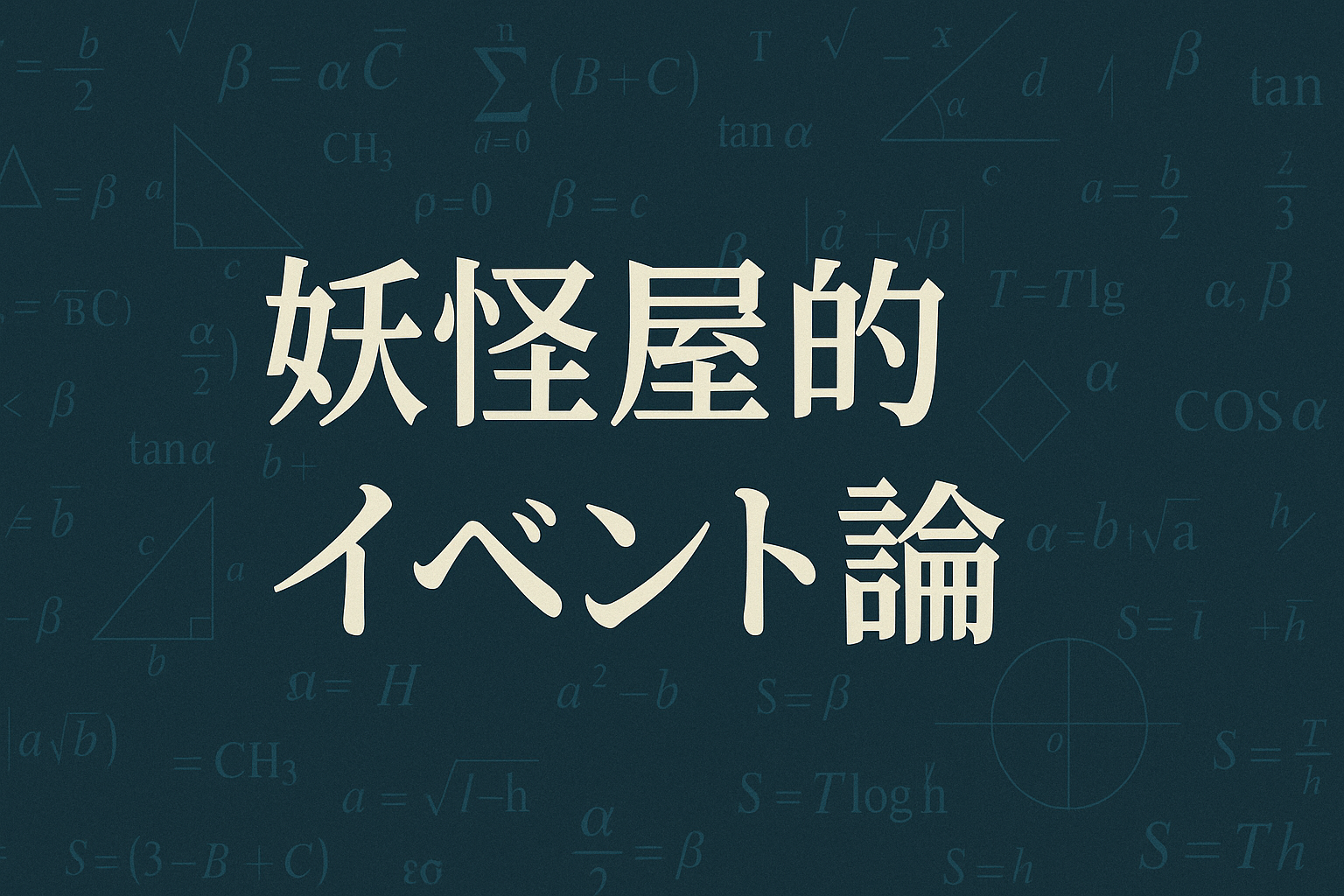
イベントというものは、楽しいだけのものではありません。参加者の笑顔に満ちた一日も、その裏側では、多くの葛藤や責任が渦巻いていることを、私は自身の地域妖怪イベントの運営を通じて、何度も痛感してきました。
たとえば、ひとつのイベントが開催されるとき、それを「楽しかった」と感じる人がいる一方で、どうしても「嫌な思いをした」と感じる人が出てしまう。どれだけ準備を重ねても、どれだけシミュレーションをしても、100%完璧な運営というのは、正直なところ、見たことがありません。
内部に渦巻く反省と責任の所在
運営側は、そんな「嫌な思い」をさせてしまったことに対して、たいてい内部で深く反省しています。関係者同士で情報を集め、「どこが悪かったのか」を真剣に検証するのです。しかし、それがエスカレートすると、最終的には「誰のせいだったのか?」という、責任の所在をめぐる探り合いになってしまうこともあります。
こうなると、やはり責任を取るべきは「主催者」や「リーダー」ということになるのですが、現場の末端にいるスタッフや関係者は、どうしても自分のすぐ上の人に対して不満をぶつけがちです。下手をすれば、SNSやスペースなどで、問題の本質からずれた文句の応酬が起こることもあります。
現場に降りかかる理不尽な矢面
さらに厄介なのは、問題の発端となった人物や、責任を取るべきリーダーが、その状況を遠くから「高みの見物」している場合です。その一方で、現場の担当者は、どうにもならなかった事態をすべて背負わされ、謝罪や対応に追われる──そんな構図も、残念ながら存在します。
イベントは準備が9割と言われますが、実際に蓋を開けてみると「これはできていなかった」「あれが危なかった」「会場が暑い・寒い」といった問題が次々に噴き出します。お恥ずかしながら、準備の段階で「ちょっと考えればできたかもしれないこと」が、できていなかったという場面も、私自身何度も経験してきました。
チリも積もれば──批判が生むプレッシャー
そういうとき、参加者の方から「こうしたらよかったのに」と言われれば、「たしかに……その通りです。申し訳ありません。そして、教えてくださってありがとうございます」というのが正直な気持ちです。でも、そのひとつひとつが積み重なると、大きな圧力になってのしかかってきます。「どう責任とるんですか?」というような、強い口調になることも珍しくありません。
私の経験では、どんなにイベント慣れしている人でも、まったく失敗のない運営をした人を見たことがありません。むしろ、完璧に成功しているように見えるイベントの裏でも、何かしらのトラブルは起きていて、それをうまくリカバリーしているだけなのです。
「ごめんなさい」が言えなくなるとき
批判の声が大きくなってくると、「ごめんなさい」が言いづらくなります。「本当はこうしたかった」「できなかった事情があった」と弁明したくなる。でも、それを口に出せば言い訳に聞こえてしまうのが、またつらいところです。心の奥にそれを押し込め、なんとかやり過ごす人。「俺のせいじゃない」と割り切れる人。さまざまなタイプがいますが、私は、やはりちゃんと伝えたいのです。
イベントは誰のためにあるのか
イベントを運営している人の多くは、「誰かを嫌な気持ちにさせたくて」やっているのではありません。むしろ、誰かに喜んでほしい、楽しんでほしいという思いから始まっています。
参加者の方が、当日の小さな不備に気づいたとき、それが共感の波紋として広がり、大きなうねりになって運営側に届く──それは当然のことですし、私たちイベンターは、それを受け止める覚悟を持って、現場に立っています。
もし、その覚悟を持っていない人がいたとしたら、それはきっと、本物のイベンターとは言えないでしょう。
互いの思いをつなぐ橋として
イベントは一度きりの「お祭り」ではありますが、そこで交わされる感情や言葉の数々は、長く心に残るものです。だからこそ、主催者側も参加者側も、互いの立場や努力、失敗と向き合いながら、ほんの少しでも歩み寄れたらと願っています。
その小さな歩み寄りが、イベントそのものを、そして地域や文化を、少しずつでも豊かにしていく──そう信じて、私は今日もイベントを企画し、準備を重ねているのです。
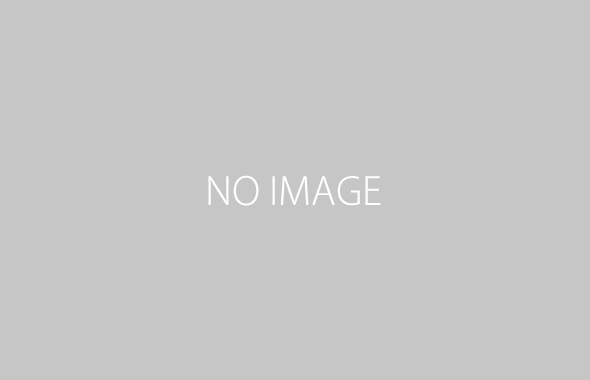
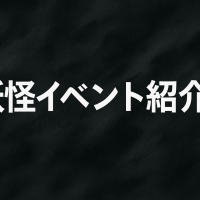

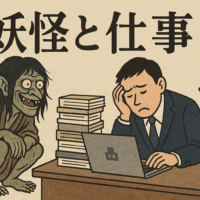
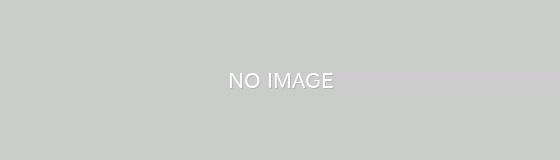


この記事へのコメントはありません。