
職業:妖怪。——「妖業師」という働き方をはじめてみた話
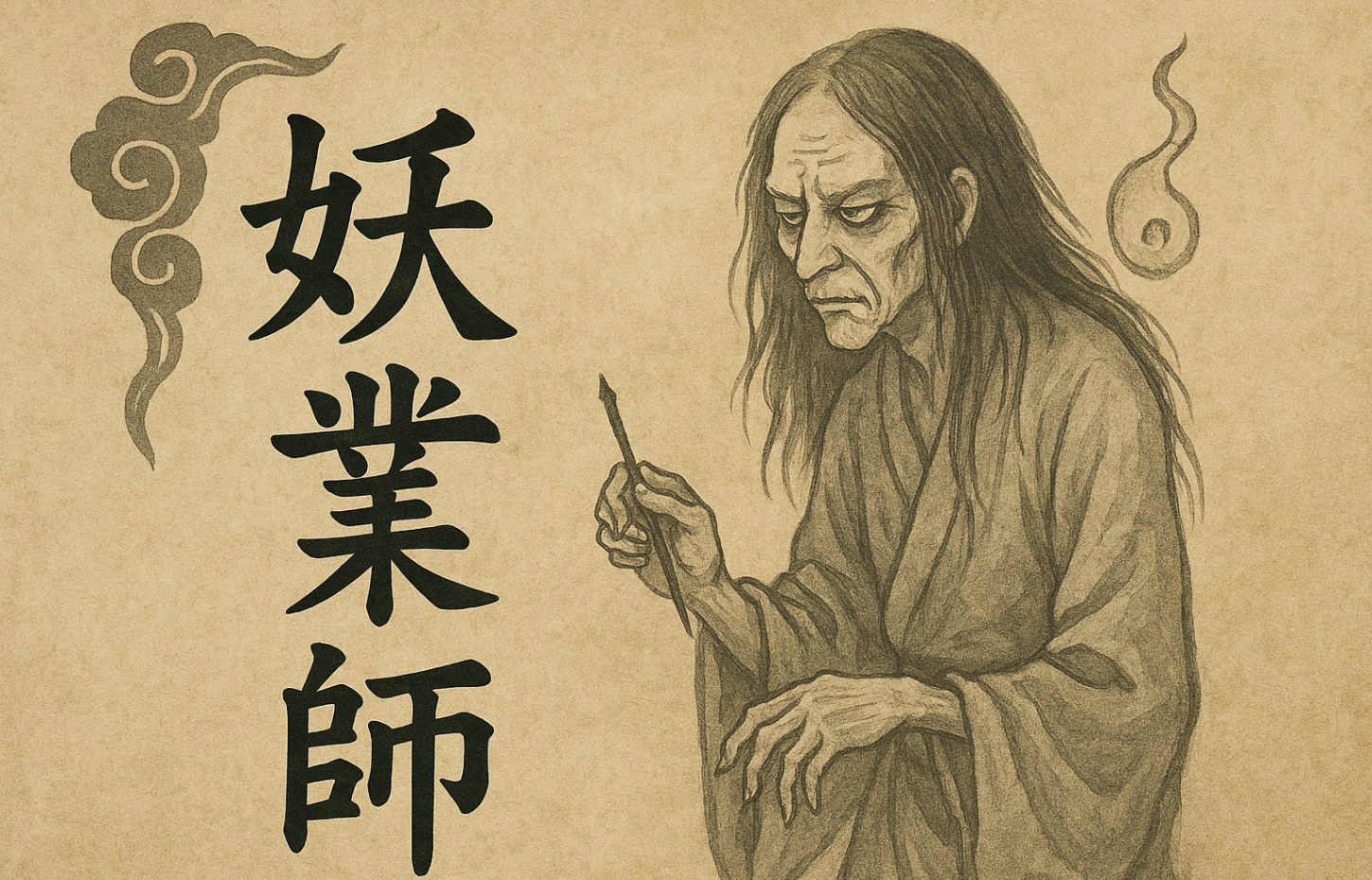
「妖怪って、仕事になるの?」
そんな風に聞かれることが、最近ちょこちょこ増えてきた。
たしかに、普通に暮らしてたら“妖怪になる”なんて選択肢、なかなか出てこないよね。
でも、ぼくは今、それを“職業”にしようとしてる。
職業:妖怪。資格名:「妖業師(ようぎょうし)」。
今日はそんな、ちょっと不思議で、でもすごく人間くさい仕事について書いてみたい。
「妖業師」って何?
「妖業師」って何かっていうと、一言でいえばプロの妖怪キャストだ。
お祭りやイベント、撮影会なんかで“本物の妖怪”として登場し、パフォーマンスをしたり、写真を撮られたり、時にはお客さんを驚かせたりもする。
大事なのは、ただの仮装ではないということ。
衣装を着て「はい妖怪です〜」ってやるんじゃなくて、その場の空気や物語の文脈を背負って、ちゃんと“存在する”ってことが求められる。
妖業師、ついにデビュー
そしてついに、このゴールデンウィーク。
5月3日、ぼくたちのプロジェクトでオーディションを重ねて選んだ3名の「妖業師」が、ついに現場デビューを果たした。
会場は、東京・麻布台ヒルズにある大垣書店さん。
そこで行われた肝試しイベントで、彼らは“異界の案内人”として参加したんだ。
(写真左:分葱(お面、しんぽうなおこ)、写真中央:杜若菖蒲、写真右:カメレオール)



子どもたちが「冒険者」になる空間
今回は、初めての本格現場ということもあり、子どもたちが怖がりすぎないように工夫した。
配置した妖怪たちは、あえて優しめの存在感で動きを抑え、物陰から見守るようなスタイルに。
結果的に、子どもたちは怖がるどころか、
「ここにもいるかも!」「こっちの棚の裏、見てみよう!」と、冒険心や探究心が勝った状態で、のびのびと暗くなった本屋さんを回っていた。
照明を落とした本棚のあいだを歩く子どもたちの足取りは軽く、ちょっとした冒険の世界みたいだった。
見えた課題と、確かな手応え
もちろん、反省点もある。
3名とも、それぞれの動きや妖怪のキャラ理解度に違いがあり、立ち位置や演出意図を伝える方法にはまだ改善の余地があった。
ギャランティの設定も含めて、現場を重ねることでブラッシュアップしていく必要があるなと感じている。
でも、それでも。
現場はとてもいい雰囲気だった。
来場者もスタッフも終始笑顔で、妖怪に囲まれながら、ちょっと不思議で優しい時間が流れていた。
主催の妖怪美術館さんや、場所を提供してくれた大垣書店さんからも、温かい言葉をいただけて、
「やってよかったな」と心から思えた。
「妖怪になる」という生き方
まだまだ、「妖業師」という働き方は始まったばかり。
制度も報酬も育成方法も、ぜんぶこれからだ。
でも、誰かがやらないと、こういう仕事は社会に存在し続けない。
ぼくはそれを、今つくっている最中なんだと思う。
たとえば将来、子どもが「将来の夢、妖怪になりたい」って言っても笑われない世界があったら、
なんか、それって良くない?
そんなわけで、今日のブログはこのへんで。
「妖怪になる」という選択肢、あなたの人生にも、ちょっと取り入れてみませんか?
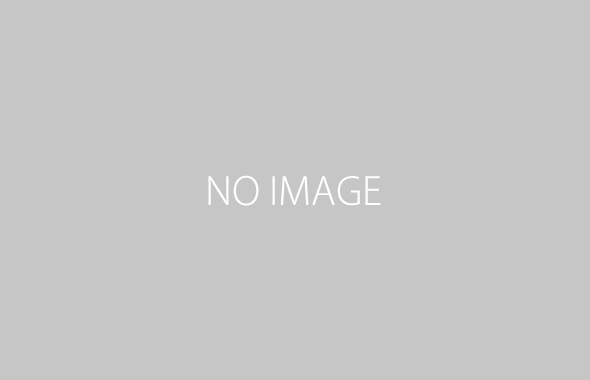

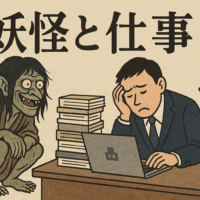
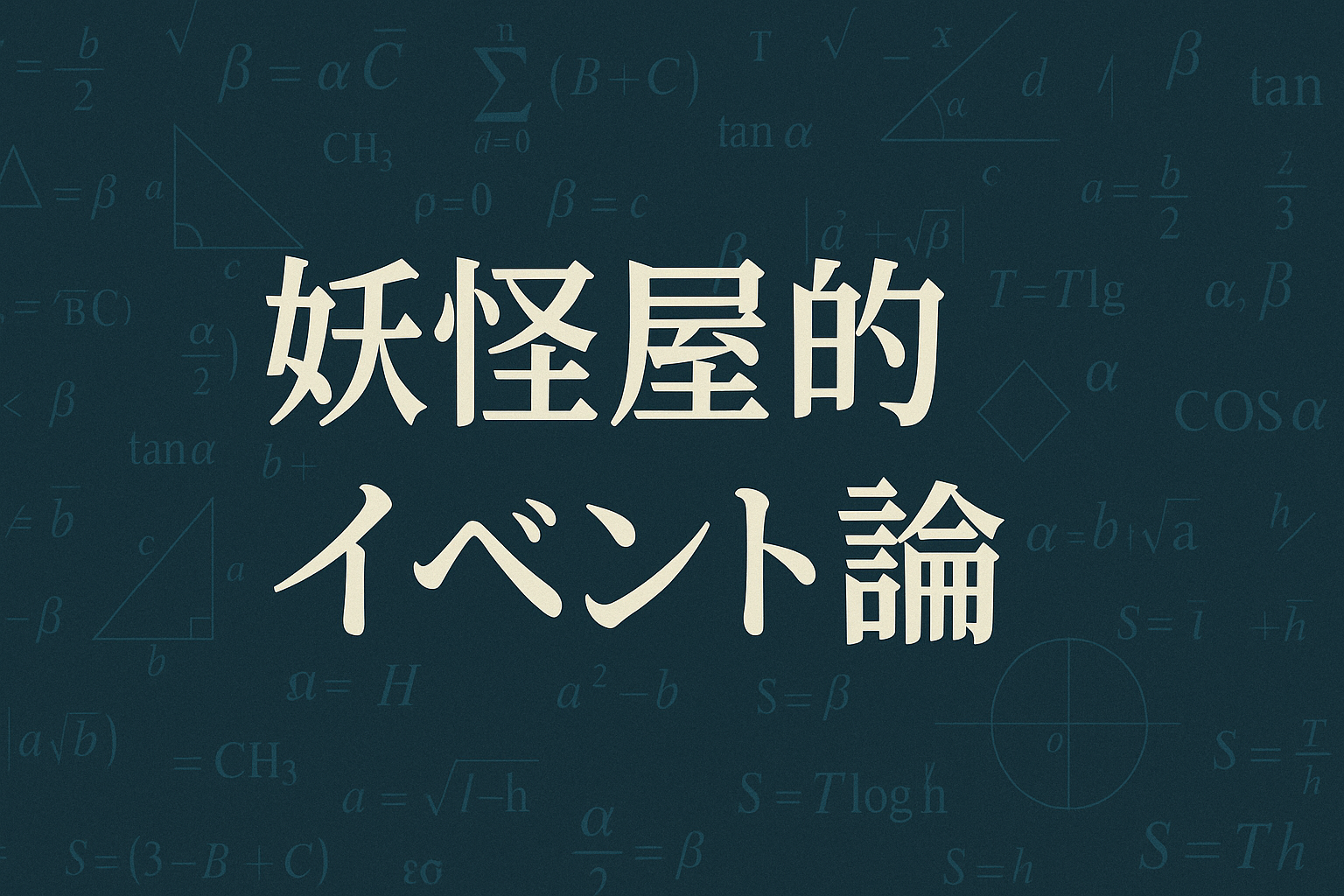
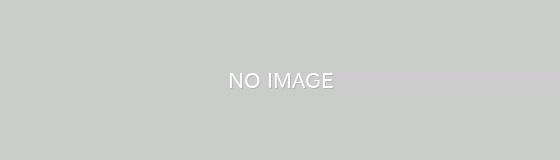


この記事へのコメントはありません。