
江戸の七不思議を巡る:本所、川越、馬喰町に見る怪異の共通点と地域性

馬喰町七不思議と私の出会い
先日、東京・馬喰町で開催された地域交流イベント「地域交差点食堂」に参加した。テーマは「妖怪屋と地域の関わり」。会の最後、地元の方々との懇親会で雑談が盛り上がる中、「馬喰町の七不思議」について語る機会があった。
実は、イベントの前に馬喰町の妖怪を調べていて、中々でてこないときに、Xの民より有力な情報として馬喰町七不思議
それがきっかけで、私は七不思議という存在に改めて興味を持った。家に帰ってから、「そもそも東京にはいくつの七不思議があるのか?」「同じ話が別の地域にもあるのか?」と疑問が次々に湧いてきて、調べてみることにした。
七不思議とは何か?
「七不思議」は、文字通り“不思議なことが七つある”という意味だが、実際には八つ、九つあることもしばしば。これは“七”という数字が昔から神秘性や完成を象徴する数字として扱われてきたため。
江戸では地域ごとに「◯◯七不思議」が存在し、本所七不思議、谷中七不思議、八丁堀七不思議、千住七不思議、川越七不思議などが有名だ。
本所七不思議の概要
墨田区に位置する本所の七不思議には、「送り提灯」「置いてけ堀」「狸囃子」「落葉なしの椎」「足洗い屋敷」「消える火の玉」「片葉の葦」といった話がある。中でも「片葉の葦」は特に有名で、隅田川沿いに生えた葦がなぜか一方の葉だけしかないという怪異だ。
川越七不思議の概要
一方、埼玉県の川越にも七不思議が伝わっている。その中には、なんと本所と同じ「片葉の葦」が登場する。伝承によると、川越城に仕えた姫が戦乱の中で命を落とし、その怨念により湿地帯に生える葦が片葉になったという。
「片葉の葦」に見る共通構造
このように、同じモチーフの怪異が異なる地域に伝わっているのは非常に興味深い。共通しているのは、水辺に関係する場所であり、女性の悲劇や怨念が背景にあること。そして自然現象を怪異として語り直すという日本文化の特徴がよく表れている。
七不思議は地域文化の縮図
それぞれの七不思議は、地域の歴史・風土・人々の記憶が反映されたミニチュアのようなものだ。馬喰町のように都市的な雑多さが滲む怪異もあれば、本所や川越のように、情念や死生観が色濃く反映される話もある。
七不思議をめぐることは、地域文化を再発見する旅でもある。あなたの街にも、まだ知られていない七不思議が眠っているかもしれない。
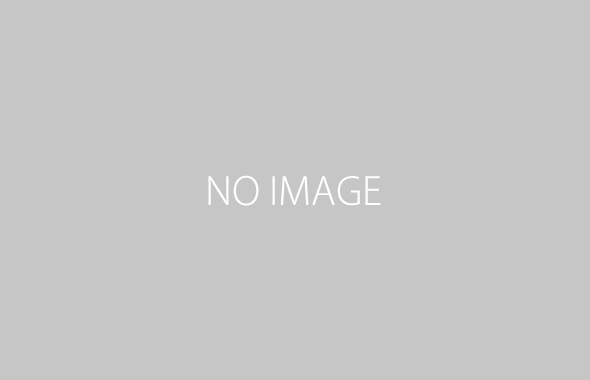
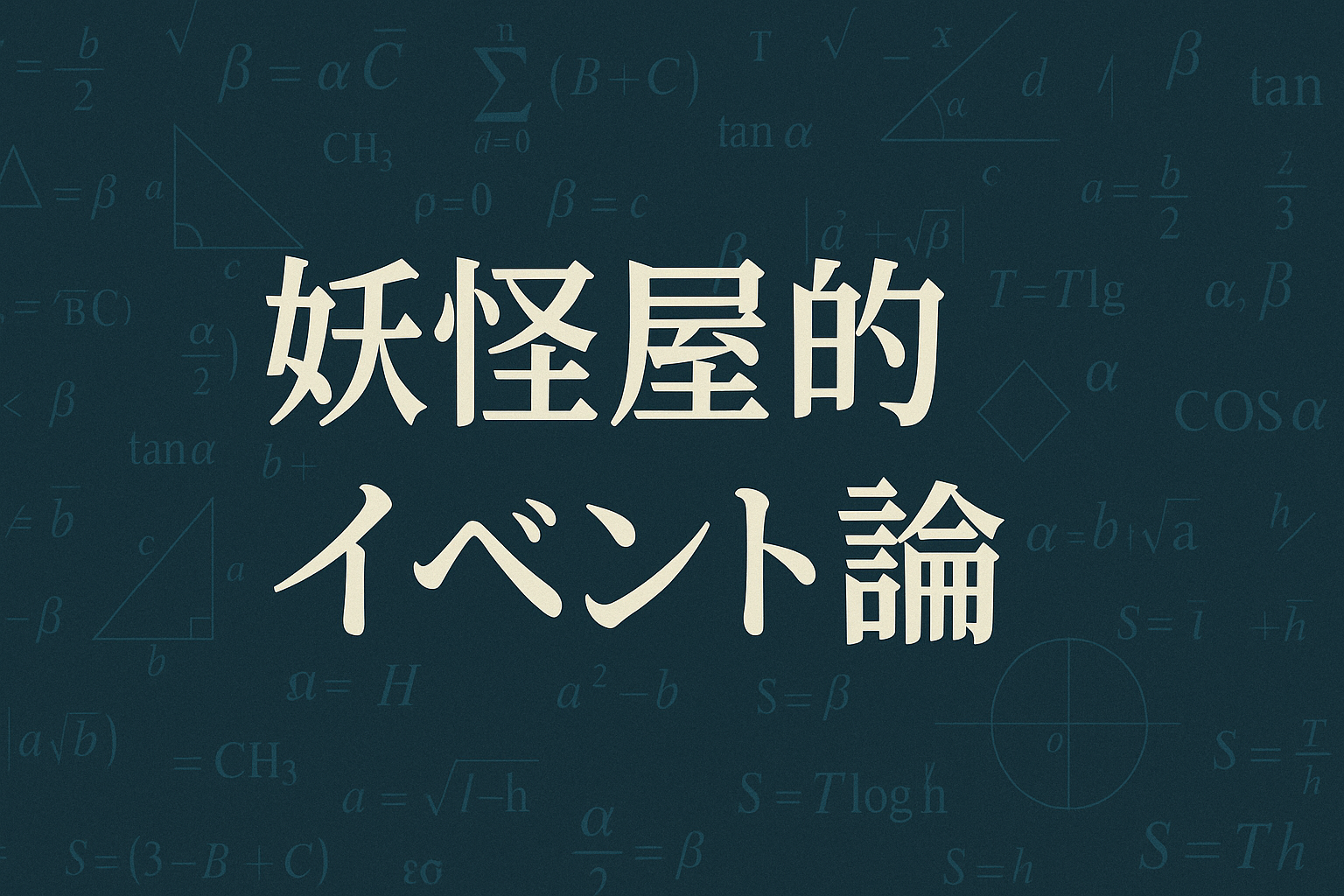
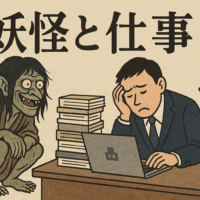

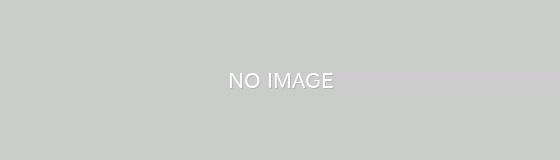


この記事へのコメントはありません。