
妖怪と歩く川越――庚申塔から天狗伝説、神隠し、そして絶品長寿グルメ!

川越の町には、妖怪という言葉では括りきれない、実際の信仰や伝承が静かに息づいています。観光地としての顔の裏にある「まちの記憶」をたどりながら、今回は庚申信仰、天狗、神隠しといったリアルな民俗信仰の痕跡を巡るまち歩きコースをご紹介いたします。
時の鐘と庚申塔――鐘の音が封じる三尸の虫
川越といえば、まず頭に浮かぶのが「時の鐘」。現在も朝6時、正午、午後3時、午後6時の4回、澄んだ鐘の音が街に響き渡ります。その鐘楼の背後に、目立たぬようにひっそりと佇むのが薬師神社。さらにその境内には、三猿(見ざる、言わざる、聞かざる)と青面金剛が彫られた庚申塔が建っています。

庚申信仰は中国の道教に端を発し、日本では平安時代から信仰されてきました。人間の体内に棲むとされる三尸(さんし)の虫が、庚申の夜に天に昇り、その人間の悪行を天帝に告げる。そう信じた人々は、庚申の夜に寝ずに集まり、講(庚申講)を開いて三尸の虫の脱出を防ごうとしました。その痕跡が、今も庚申塔として町中に残っているのです。
川越市内には、実に92基の庚申塔が確認されており、連雀町から仙波町にかけては多くの塔が点在しています。特に寛文から元禄、明治期までの石塔には、時代ごとの造形美や信仰の変遷が刻まれており、庚申講という民間信仰の奥深さを感じさせてくれます。
広済寺と天狗――火除けの守護者
川越の蔵造りの町並みを少し外れたところに、ひっそりと佇む広済寺。ここには「天狗が火災から街を守った」という伝承が残されています。
かつて川越の町は火災が絶えず、町人たちは火伏せの神仏に祈りを捧げてきました。広済寺には、天狗が羽団扇で風を起こして火の手を逸らしたという逸話があり、その意匠は門柱や寺の装飾にも見て取れます。火を防ぐ存在としての天狗――その役割は、鬼としてではなく、むしろ土地を護る守護者として語り継がれています。
また、天狗の伝承とともに語られるのが「だいれんじ火」という言葉。これは寺周辺に出没したとされる不審火の呼び名であり、何かしら霊的なものの仕業と考えられていたようです。現在では失われた言葉となりつつありますが、その響きはまさに、まち歩きの途中でふと背筋が伸びるような感覚を与えてくれます。
鴉山稲荷神社――神隠しの丘
川越城の築城の際、藩士が森の伐採にあたっていたとき、忽然と姿を消したという伝説が残るのが鴉山稲荷神社。鳥が群れるこの小高い丘に鎮座する神社には、今も「神隠し」の空気が漂っています。
神隠しとは、突然人が姿を消す現象。古くは神の世界に引き込まれたとされ、時に妖怪の仕業とも、あるいは異界との接触とも解釈されてきました。川越の町の端に位置するこの神社は、町の喧騒から一歩離れた異空間のような趣があり、狛狐の前に立つと時の流れがゆっくりと変わるような感覚に包まれます。
伝承とともに味わう、川越のうなぎと武蔵野うどん
まち歩きの合間には、地元の味覚を楽しむのも旅の醍醐味です。川越といえば、江戸時代から続くうなぎ文化が根付いており「健康と長寿の象徴」として味わうことができます。
代表的なうなぎの名店を以下にご紹介しましょう。
- 小川菊:文化4年(1807年)創業。香ばしい皮とふんわりとした身が絶妙。
- いちのや:天保3年(1832年)創業。蒸し焼き製法とひつまぶしも人気。
- 東屋:慶応4年(1868年)創業。濃厚なタレと香ばしい焼きが特徴。
- 林屋:備長炭使用。家庭的な雰囲気で気軽に楽しめる。
- ぽんぽこ亭:国産鰻使用。ワインと合わせて楽しめるモダンなスタイル。
そしてもう一つ、忘れてはならないのが「武蔵野うどん」。地粉のどっしりとしたコシと肉汁の濃厚さが魅力です。特に以下のお店が人気です。 埼玉県は、うどん(麺類)の生産量が全国2位、消費量が全国5位!相当なうどん王国と言えます。
- 長谷沼:本川越駅すぐ。天然出汁と讃岐系のコシが楽しめる。
- 藤店うどん:川越駅から徒歩圏。行列必至の武蔵野うどんの名店。
- 土麦(つむぎ):地元産素材とモダンな空間が魅力の新鋭店。創作系うどんと丁寧なだしが好評。
- うどん辰未:本川越駅徒歩4分。煮干し出汁の香る一杯と店内揚げ天ぷらが魅力。食べ歩きにも対応したスタイルで気軽に楽しめる。
伝承と地元グルメが重なることで、ただの観光ではない「まちを味わう旅」が完成します。
結びにかえて
妖怪とは、必ずしも「恐ろしい存在」ではありません。それは、地域に根付き、土地と人とをつなぐ媒介でもあります。庚申信仰に天狗、神隠し。川越の町には、そうした目に見えない記憶の層が、確かに存在しています。次に川越を訪れるときは、ぜひその“気配”に耳を澄ませながら、まち歩きと食を楽しんでみてください。
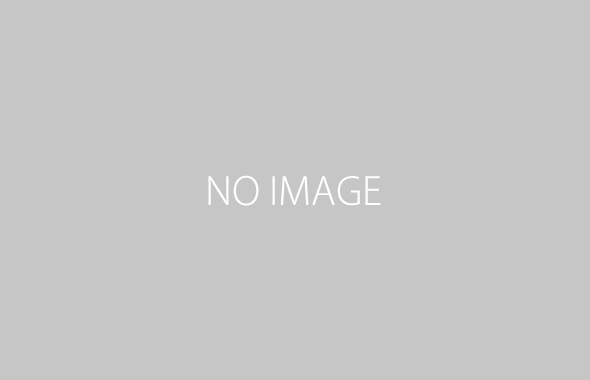
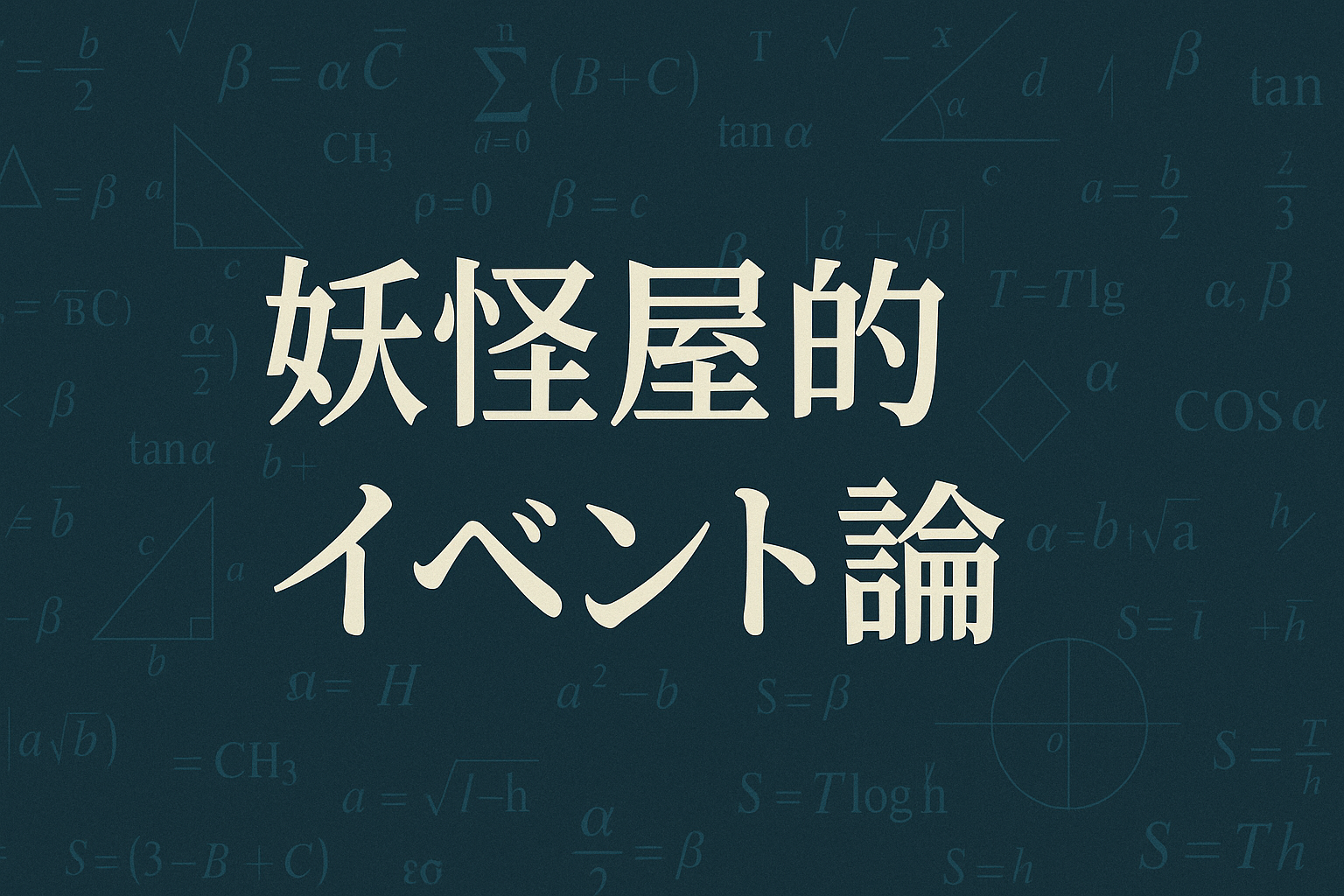
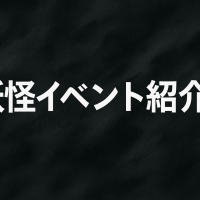

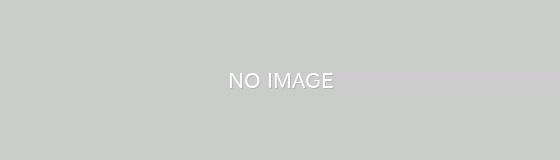


この記事へのコメントはありません。