
妖怪とワインの逢瀬──芳醇なる夜の妖し

ワインと妖怪。この取り合わせを耳にして、少々奇異に感じる方もおられるでしょう。しかし、2025年夏、山梨で開催される「とあるワインイベント」にて、弊社はこの異色の組み合わせをテーマに新たな企画へと挑もうとしています。その名も「妖怪とワインの邂逅(かいこう)」。本稿では、このコラボの背景にある歴史と文化、そしてその可能性について考察してみたいと思います。
ワインが海を越えてやってきた頃(16世紀)
日本にワインが初めて伝わったのは、1549年。フランシスコ・ザビエルらキリスト教の宣教師が、日本に持ち込んだ葡萄酒がその始まりとされています。儀式や外交に用いられたワインは、大内義隆や織田信長といった大名たちに献上され、異国の珍品としてもてはやされました。
この時代、ちょうど妖怪文化も百鬼夜行絵巻や妖怪草子といった形で絵画や物語の中に姿を現し始めた頃でもあります。未知なるもの、異質な存在との出会い。ワインと妖怪は、いずれも「異文化」との邂逅の象徴だったのかもしれません。
江戸時代:ワインの沈黙、妖怪の開花(17〜19世紀)
やがて鎖国政策が布かれ、西洋の酒であるワインは日本の表舞台から姿を消します。しかしこの頃、妖怪たちはむしろ庶民文化の中で花開きます。浮世絵、草双紙、落語など、多様なメディアを通じて妖怪は人々の想像力を刺激し続けました。
この時代の妖怪は、風習や災害、病気など、人々が日常で感じる“不可視の脅威”を擬人化したものが多く登場します。ワインは静かに発酵を続け、妖怪は人々の口の端にのぼり、共に“目には見えぬもの”を通して文化を紡いでいたのです。
明治時代:再び現れる異国の味と姿(19世紀後半〜20世紀初頭)
明治維新を機に再び海外との接触が増え、日本の地でも本格的なワイン醸造が始まります。1877年、山梨にて設立された「大日本山梨葡萄酒会社」がその嚆矢。日本固有の風土を活かしたワイン造りが始まりました。
一方で、この時代は西洋妖怪や新種の怪異も登場し始める頃。文明開化の波に揺れる社会は、近代化への戸惑いと不安を“妖怪”というかたちで昇華していたとも言えるでしょう。ワインと妖怪——両者ともに、時代の変革期に人々の想像力を支える存在だったのです。
現代:日本ワインと妖怪の再定義(21世紀)
現在、日本ワインは世界的な評価を得るまでに成長し、特に甲州種やマスカット・ベーリーAといった日本独自の品種が注目されています。ワイナリーは単なる醸造所ではなく、観光・文化・教育の拠点となりつつあります。
妖怪もまた、現代においてはアニメや地域振興のシンボルとして再評価されつつあります。人々の記憶と風景の中に、ゆるやかに溶け込んでいるのです。
ワインと妖怪、味わい方の共通点
ワインと妖怪には、実に多くの共通点があります。
- 見えないものを感じ取る愉しみ:ワインの奥にある風土や作り手の思い。妖怪の姿の背後にある民間信仰や自然観。
- 時間と共に変わる奥行き:熟成によって味が変わるワイン。時代によって役割が変化する妖怪。
- 物語とともに味わう愉しさ:背景を知ることで深まる味と魅力。
- ちょっと怖くて、ちょっと魅惑的な二面性:酔いと覚醒、畏怖とユーモア。
これらの共通点は、まさに“日本的な感性”そのものだと言えるでしょう。
妖怪とワイナリーの未来——発酵する物語と風景
未来を見据えると、「妖怪✕ワイナリー」は多くの可能性を秘めています。
- 地域ブランディング:地元妖怪の名を冠したワイン商品(例:猫又ルージュ、雪女シャルドネ)
- 体験型観光:百物語ワイナリーナイト、妖怪収穫祭など
- デザインと物語性の融合:味覚の妖怪的擬人化、「酸味の妖怪」「渋味の鬼」など
- 教育的展開:「ワインと妖怪文化史」講演、絵本・葡萄ジュースによる家族向け企画
- 海外発信:「Yōkai & Wine」ツアーや国際ラベル展開
妖怪とワイン。どちらも、人の想像と感性が育てた「文化の発酵食品」と言えるのではないでしょうか。その出会いは、過去を語り、今を楽しみ、未来を描く鍵となるはずです

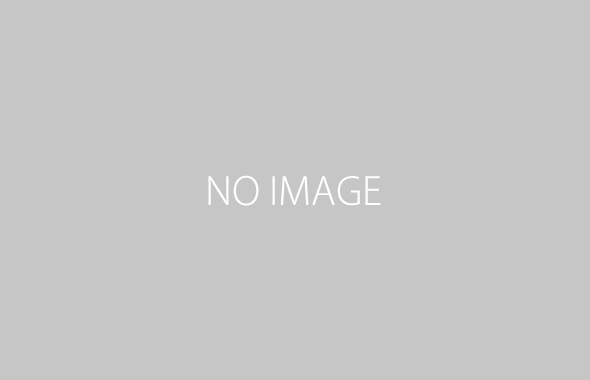
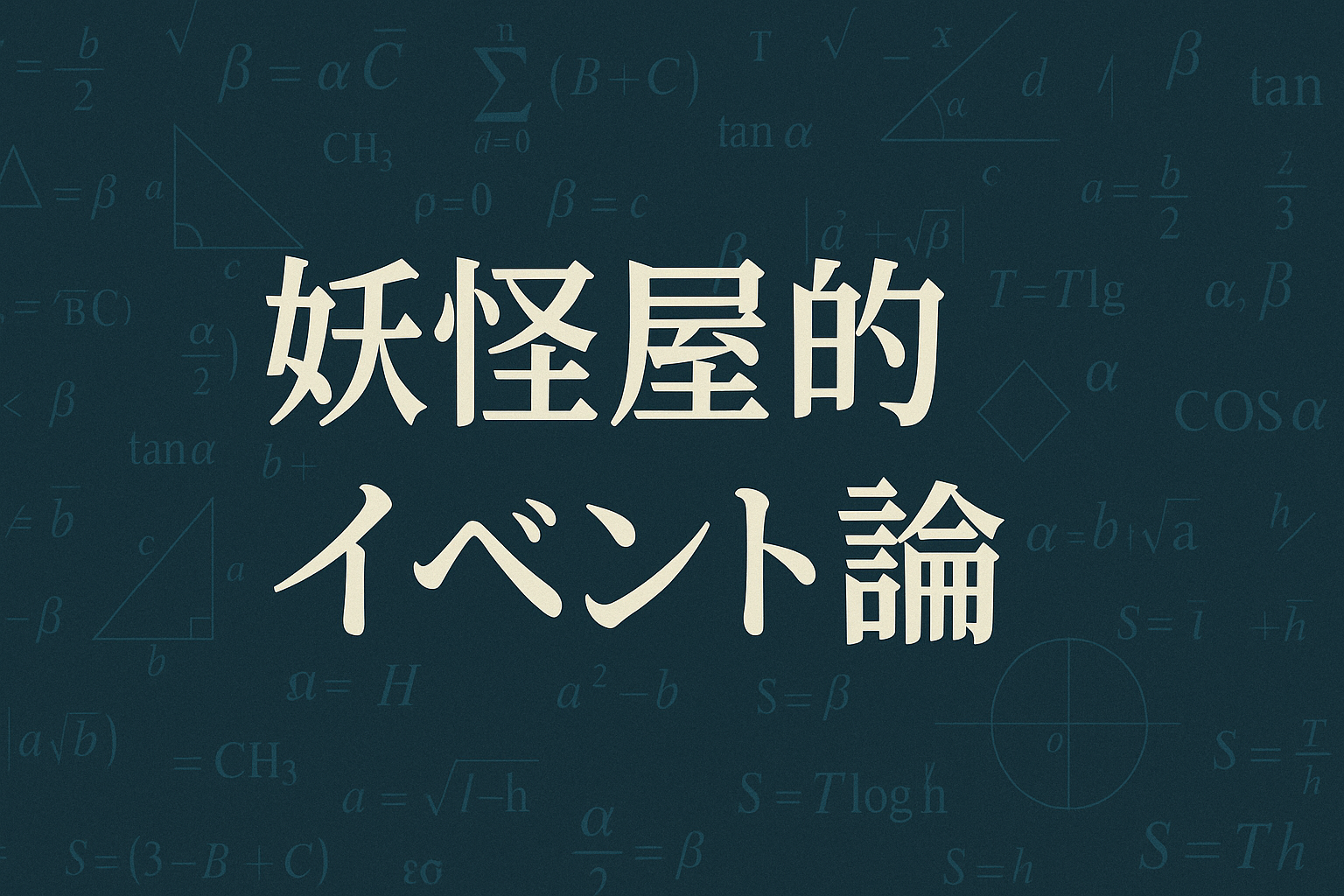
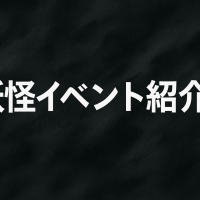

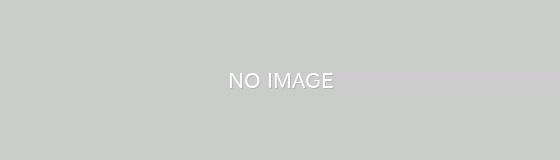


魅力的な文章で紡がれていった2つの文化。
読み手と共に歩む歴史ツアーを体感しているかのように、想像が創造されていきました。
初見ですが、どちらも新鮮で
早朝からコメントせずにはいられませんでした。
愉しみにしています。