
温泉地から日本人が消える日──オーバーツーリズムと地域文化の危機

温泉地から日本人が消えていく
いつからでしょうか。 日本の温泉地が、「もう日本人のための場所じゃなくなってきた」と感じるようになったのは。
妖怪をテーマにした地域イベントを続けてきた弊社(妖怪屋)は、地元の方々とふれあい、観光客の声に耳を傾けてきました。そのなかで見えてきたのは、「地域の文化が、静かにすり減っている」という現実です。
かつては、地元の常連客が家族連れで訪れ、気軽に泊まれた温泉地。ところが今や、宿泊費は劇的に上昇しています。たとえば東京のビジネスホテルでは、2021年1月の平均が約6,340円だったのに対し、2023年12月には約15,400円とおよそ2.5倍に跳ね上がっています。このような急激な価格上昇は、こと温泉地においても同様に発生しています。
日本人が“泊まれない”観光地とは、一体何なのでしょうか。
不明瞭な値上げと、疲弊する地域
2024年のゴールデンウィークには、約2,280万人(前年比0.9%増)の国内旅行者が訪れましたが、地方の温泉地では宿泊施設の予約が伸び悩み、日帰りの利用者も減少していると報告されています。
さらに深刻なのは、日帰り入浴すら気軽に楽しめなくなっているという点です。源泉かけ流しの温泉地で、サービス内容に変化がないにもかかわらず、値上げが相次いでいます。燃料費についても、ここ最近は大きな高騰は見られず、直接的な影響は限定的です。また、人件費についても大幅な上昇は確認されておらず、厚生労働省の統計によれば、宿泊業や飲食サービス業の平均賃金は依然として産業全体の平均を下回る水準に留まっています。にもかかわらず、価格だけが吊り上がっていく現状には、地元の方々も「便乗では?」と疑念を抱かざるをえません。
物価高騰や増税が重なり、日本人の所得は確実に減少しています。観光地にとって本来大切にすべき地域住民や国内観光客が、次第に足を遠ざけていく現状があります。
インバウンド依存の危うさ
さらに問題を複雑にしているのが、経営の実態です。インバウンド対応を掲げながらも、実際には接客体制が整っていなかったり、海外資本に売却され、地域の意思が届かない形で運営されている施設が増えてきました。
こうした場所では、文化や風習は徐々に失われ、土地はただの“観光商品”となっていきます。インバウンド需要が冷え込んだあとの未来に待つのは、“文化の空洞化”かもしれません。
妖怪屋が続けてきた妖怪イベントの意味
弊社は、妖怪という文化資源を通じて、地域の物語、日本の原風景を伝える活動を続けてきました。妖怪はただの“怖い存在”ではなく、人々の生活のなかから生まれた、土地へのまなざしそのものです。
日本の観光地が本当に大切にすべきものは、目新しさや豪華さではなく、そこに根ざした文化や心なのではないでしょうか。日本人自身がその価値に気づき、誇りをもって接することで、初めて海外の方々にも“本物の日本”が伝わるのだと思います。
地域が守らなければ、誰も守ってくれない
地域の方々が、自分たちの町や文化を“自分ごと”として守る。その意識がなければ、どんなに素晴らしい文化も、やがては失われてしまいます。外からきたものがいくら頑張っても・・・です。
弊社の活動は小さな試みかもしれません。しかし、妖怪の語りを通じて、土地の声を拾い上げ、そこに暮らす人たちの誇りや願いを形にしていく。そんな営みが、未来の観光地のあり方を変える一歩になると信じています。
観光とは、文化を売ることではなく、文化を共に守り、分かち合うこと。 「売れる観光」から「残したい文化」へ。 その原点に、いまこそ立ち返るときではないでしょうか。
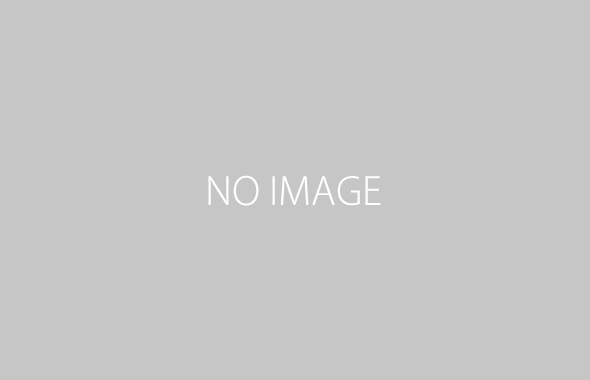
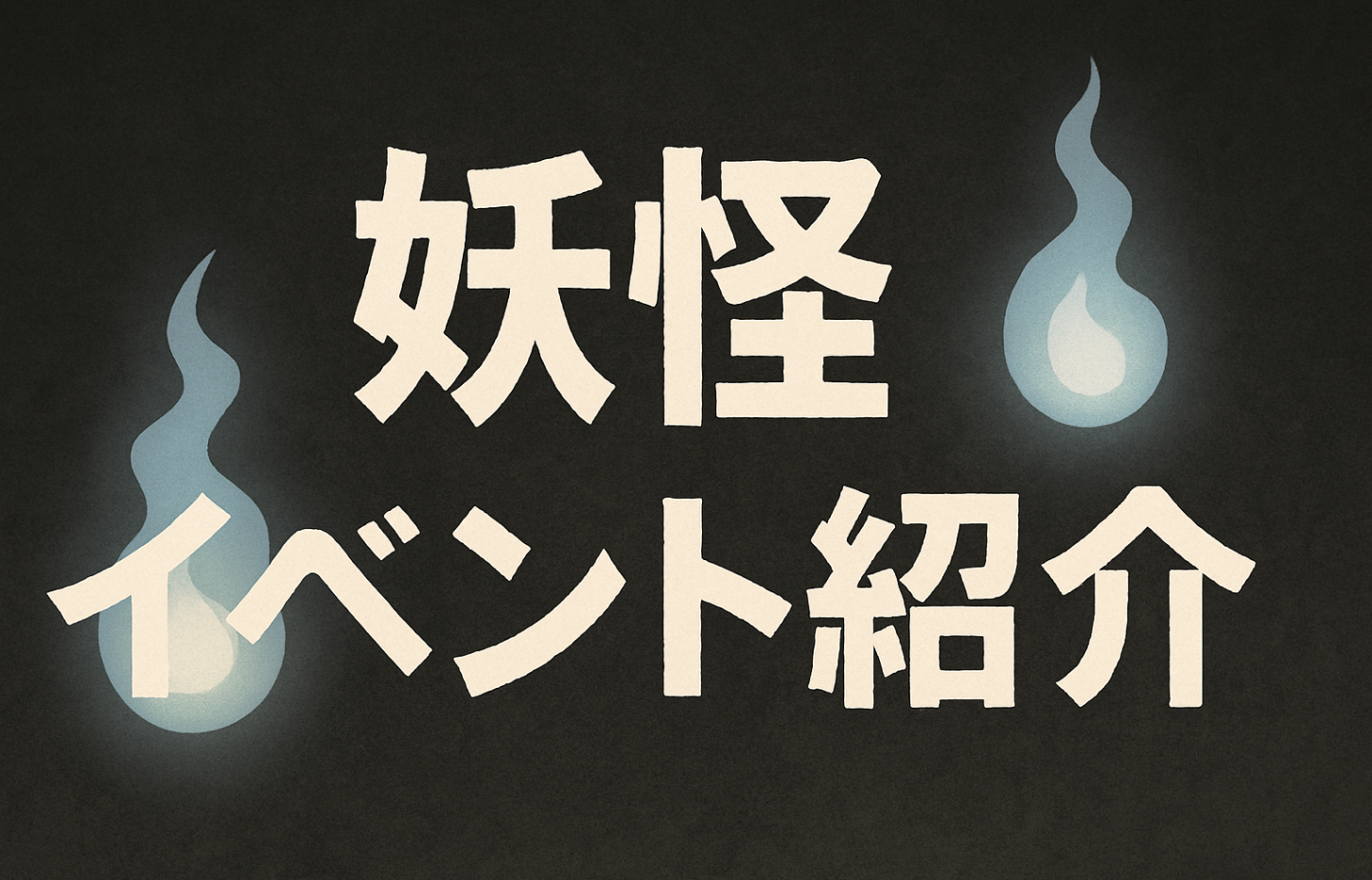
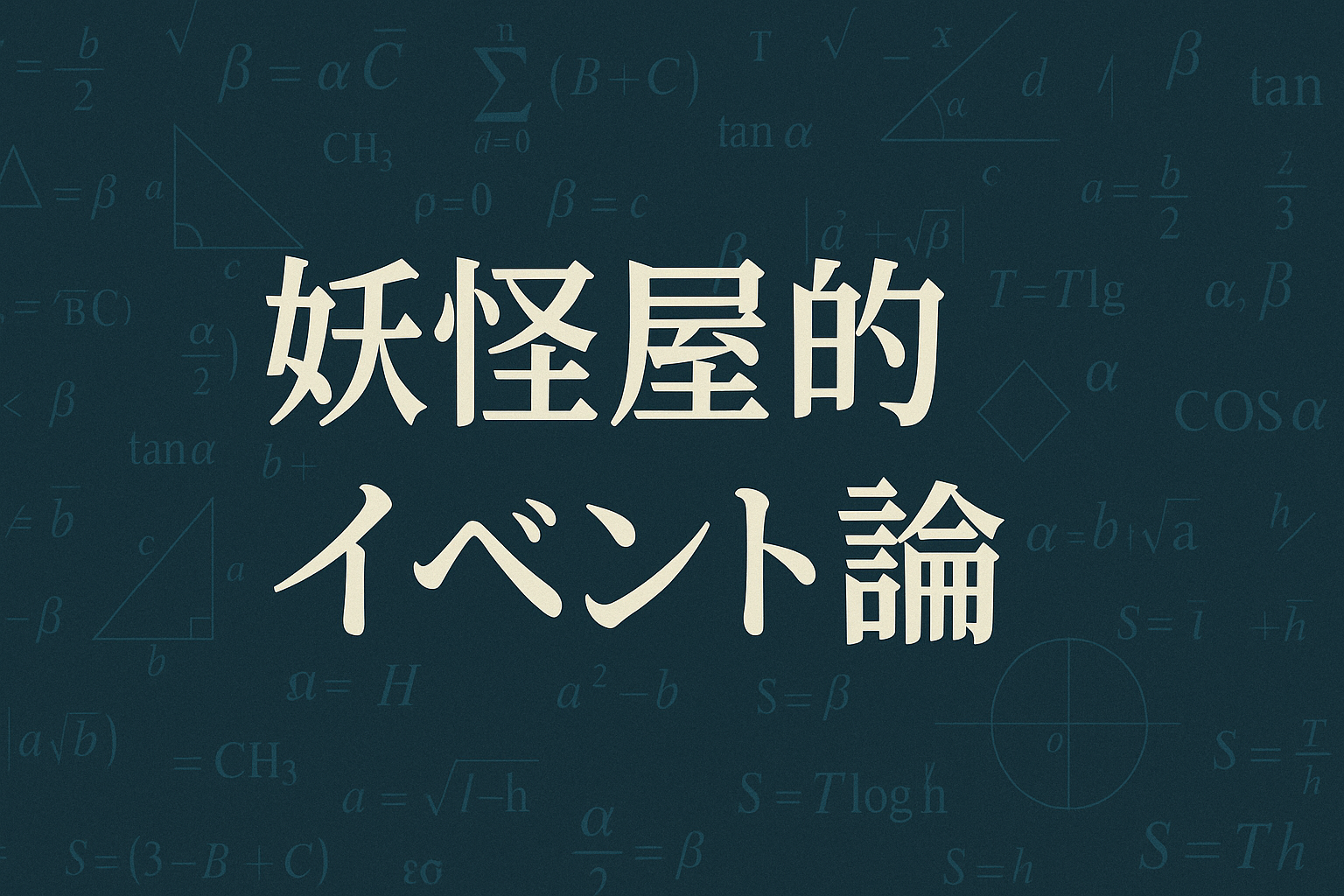
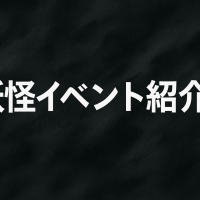

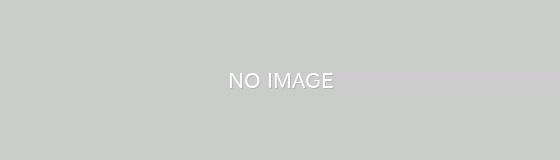


この記事へのコメントはありません。